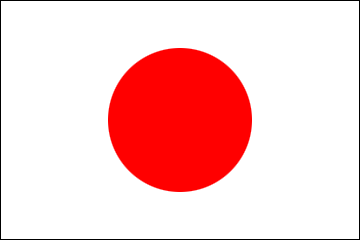南アフリカってどんな国?
1. 概観
○アフリカ及び開発途上国のニューリーダー
1991年のアパルトヘイト(人種隔離政策)撤廃と94年の民主政権の発足により、南アフリカは、対話による人種対立解決と融和の象徴の国とされている。ムベキ前大統領はアフリカ自らの力で紛争、貧困、独裁、汚職などの問題を克服しようとする「アフリカの新しい流れ」を代表する指導者として知られ、途上国と先進国との間の「南北の架け橋」としての役割を積極的に追求した。同大統領は、九州・沖縄サミット(2000年)以降の毎年すべてのG8サミットに参加。2009年4月に民主化後4回目となる総選挙が実施され、ズマANC総裁が新大統領に選出された。
○温暖な気候と豊かな自然
アフリカ大陸の最南端、インド洋と大西洋を結ぶ要衝の地に位置する。太陽の国と言われるほど年間を通じて晴天の日が多く、全体的に気候は温暖。また、2000m級の山脈、砂漠と森林、高原と平野など多様な地形と気候を反映して、動植物の宝庫でもある。自然や文化遺跡も豊かであり、「スタークフォンテン・スワークランズ・クロムドライ及び周辺地域の人類化石遺跡群(アウストラロピテクスなどの人類化石が発見された遺跡群)」、及びロベン島(ケープタウン沖にあるアパルトヘイト時代の刑務所島)などの文化遺産、「グレーター・セントルシア湿地公園」、「ケープ植物区系の保護地域群」などの自然遺産等、計7カ所が世界遺産に指定されている。

ロベン島 |

ケープ植物保護地区内のカーステンボッシュ国立植物園 |

自然・文化遺産のドラケンスバーグ公園 |
○七色の国民
広い国土と複雑な歴史により、黒人(ズールー族、コーザ族、ソト族、ツワナ族等)、白人(オランダ系、イギリス系等)、カラード(混血)、アジア系(インド人等)で構成されている。アパルトヘイトという苦難の歴史を克服し、復讐ではなく和解を追求した南アの国民は、敬意をもって「七色の国民(レインボー・ネイション)」と呼ばれている。
○アフリカ最大の経済大国
群を抜いたアフリカの経済大国であり、サハラ以南アフリカ地域諸国のGDPの約4割を占める。わが国と南アとの貿易額はわが国と同地域の貿易額の約5割、直接投資額は同地域(リベリアを除く)の約7割を占める。豊富な天然資源を有し、特に金、クロム鉱、白金(プラチナ)、バナジウム等の生産量、埋蔵量は世界上位に位置する。
|
|
鉱石生産量(世界シェア)(07年) |
埋蔵量(世界シェア) |
単位 |
||
|
金 |
292 |
(11.8%、1位) |
6,000 |
(14.3%、1位) |
トン |
|
クロム |
7,089 |
(37.5%、1位) |
160,000 |
(33.6%、2位(注)) |
千トン |
|
マンガン |
5,340 |
(16.9%、1位) |
100,000 |
(21.7%、2位) |
千トン |
|
バナジウム |
23,000 |
(39.2%、1位) |
3,000,000 |
(23.1%、3位) |
トン |
|
プラチナ |
157.9 |
(77.4%、1位) |
63,000 |
(88.7%、1位) |
トン |
|
パラジウム |
83.4 |
(38.3%、2位) |
63.000 |
(88.7%、1位) |
トン |
|
ジルコニウム |
398 |
(33.7%、2位) |
14.0 |
(36.8%、1位) |
生産量:千トン、 |
【出典:Mineral Commodity Summaries 2008他 (注)クロム埋蔵量シェアは判明分で算出】
2. 歴史
|
|
| ロベン島内の刑務所跡。20世紀半ばから、ネルソン・マンデラ前大統領を含むアパルトヘイト政策に反対する多くの政治犯が収監された。 |
○英国からの独立、アパルトヘイト
17世紀半ばからオランダ、19世紀前半からは英国の植民地となる。1910年、南アフリカ連邦として独立したが、白人政権は黒人の政治的・社会的・経済的権利を剥奪するアパルトヘイト(人種隔離政策)を実施し、国際社会から厳しい非難を浴びた。国連では69年にアパルトヘイト政策を非難する総会決議が採択され、各種安保理決議により武器等の禁輸や人的交流の禁止などの○民主的政権の発足
1990年以降、デ・クラーク大統領(当時)の下でアパルトヘイト撤廃に向けた国内改革が進展し、94年4月に初の全人種参加による総選挙が行われた結果、アフリカ民族会議(ANC)総裁として反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マンデラを大統領とする民主政権が発足した。旧白人政権時代には、弾圧とテロが頻発し、民主化前夜には「内戦は不可避」とまで言われたが、マンデラ大統領の国民和解路線の下で情勢は安定した。99年6月には二度目の総選挙が行われ、ANCから後継者として指名されたムベキ大統領が選出された(04年4月の三度目の総選挙で再任)。その後、09年4月に四度目の総選挙が実施され、現在はズマ大統領が政権を担っている。
○混迷する政局
南アの国際的地位の向上並びに着実な経済成長を成し遂げたムベキ政権であったが、07年12月のANC全国大会での総裁選でジェイコブ・ズマ副総裁が新総裁に選出されたのを契機としてムベキ大統領の党内での影響力は急激に低下、そして、汚職容疑でのズマ副総裁に対する起訴プロセスにムベキ政権の政治的圧力があったとする司法判断を背景にANC執行部は同大統領の解任を決定し、08年9月、ムベキ大統領は辞任した。ムベキ大統領の辞任は、ANC新執行部の党の運営振りに不満を抱くANC幹部の離党、新党(国民会議:COPE)結成にまで発展し、ANCが分裂する事態となった。09年4月にに民主化後4度目となる総選挙が実施され、与党ANCが約66%の得票率で勝利し、ズマANC総裁が新大統領に選出された。
3. スポーツ
○サッカー
2010年6月にはアフリカ大陸で初となるサッカーW杯が南アフリカで開催される。現在、同大会の会場となる国内10か所のスタジアム建設が急ピッチで行われている。
南ア(チーム愛称名はバファナ・バファナ(Bafana Bafana、現地ズールー語で「少年たち」の意)は98年のフランス大会に初出場し(トルシエ元日本代表監督が監督を務めた。)、02年の日韓大会にも連続出場を果たした(2回とも予選リーグ敗退)が、06年のドイツ大会出場は果たせなかった。
2000年シドニー・オリンピックの予選リーグでは日本と南アが大接戦の末、最終的には2対1で日本が勝利、2009年11月にポートエリザベスで開催された日本代表対南ア代表の親善試合は0対0の引き分け。なお、サッカーは主に黒人、ラグビーは主に白人の間で人気が高い。
○ラグビー
 南アで最も盛んなスポーツであり、実力は世界のトップクラス。アパルトヘイトに対する国際的非難の中、南アのナショナル・チーム「スプリング・ボックス」は長らく国際大会の参加資格を得られなかったが、94年の民主化以降、国際大会に復帰。95年、南アはW杯に開催国として初参加し、劇的な初優勝を果たした。99年のW杯でも活躍し、豪、仏に次いで3位の成績を残したが、03年の大会では準々決勝で敗退した。07年10月に開催されたフランス大会ではイングランドを破り2度目の優勝を果たした。
南アで最も盛んなスポーツであり、実力は世界のトップクラス。アパルトヘイトに対する国際的非難の中、南アのナショナル・チーム「スプリング・ボックス」は長らく国際大会の参加資格を得られなかったが、94年の民主化以降、国際大会に復帰。95年、南アはW杯に開催国として初参加し、劇的な初優勝を果たした。99年のW杯でも活躍し、豪、仏に次いで3位の成績を残したが、03年の大会では準々決勝で敗退した。07年10月に開催されたフランス大会ではイングランドを破り2度目の優勝を果たした。
○野球
06年3月、日本が優勝したワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に、南アはアフリカから唯一出場し、一次リーグで3戦全敗し敗退したものの、MLBの主力選手を要するカナダ相手に8-11と善戦した。
4. 文化等
○南アフリカ料理
多民族国家であるため、世界各国の料理が味わえる。一般的な食事は英米風で、休日には「ブライ」と呼ばれるバーベキューを楽しむ。野菜や豆をたくさん入れた煮込み料理が伝統的な家庭料理。興味を引くのがワニ、インパラ、ダチョウなどの猟鳥獣料理(ゲーム・ディッシュ)。
○ワイン
 ぶどう栽培に適した地中海性気候と肥沃な土地に恵まれたケープタウンとその周辺では、17世紀半ばからワインづくりが行われてきた。南アのワインは全世界のワイン生産量の約4.1%を占め、日本への輸出も増えている。その品質は世界的に認められるようになっており、国際的な賞(注)を受賞するワインも多い。
ぶどう栽培に適した地中海性気候と肥沃な土地に恵まれたケープタウンとその周辺では、17世紀半ばからワインづくりが行われてきた。南アのワインは全世界のワイン生産量の約4.1%を占め、日本への輸出も増えている。その品質は世界的に認められるようになっており、国際的な賞(注)を受賞するワインも多い。
【参考】南ア・ワインが受賞した主な国際的な賞の一例
1991年産カノンコップ(Kanonkop)ワインは、94年のロンドンにおける国際ワイン&スピリッツ・コンテスト(International Wine & Spirit Competition(IWSC))において最優秀赤ワインに与えられる賞を受賞した。
○アカデミー賞
 (主演女優賞)
(主演女優賞)
04年、南ア出身の女優シャーリーズ・セロンがアカデミー賞主演女優賞を受賞。主演作品は「モンスター」。
 (アカデミー外国語作品賞受賞)
(アカデミー外国語作品賞受賞)
06年3月、南ア映画"Tsotsi"がアカデミー賞の外国語作品賞を獲得する快挙を成し遂げた。ムベキ大統領(当時)も祝福し、経済界も南ア映画の今後の活性化に期待を示した。
(Tsotsi(ツォツィ):赤ん坊を誘拐してしまったことにより、人の命の重みについて学んでいく青年を描いたヒューマン・ドラマ)
5. 日本との関係
○JETプログラム
南アは1997年からJETプログラムに参加しており、これまで300名の参加者が日本各地の学校で英語及び国際教育に活躍し、両国国民間の理解促進の一助となっている。09年7月には、新たに41名の参加者が渡日した。
○日本の伝統文化
生け花、盆栽、鯉、囲碁等の協会が存在し、それぞれ日本の本部と交流がある。南ア各地でデモンストレーション、セミナー等を定期的に実施している。
○武道
日本の武道の愛好者は意外に多く、空手、柔道、柔術、相撲、剣道、沖縄古武術等の協会が存在して、日本の本部と交流している。空手協会は、黒人居住地区(タウンシップ)でも青少年育成の一環として教えられている。
○日本にあった最古のアフリカ地図
現存する最古のアフリカ大陸の地図の一つが日本にあると言われている。「混一疆理歴代国都之図」と呼ばれるこの地図は、元々1402年に朝鮮使として明に派遣された金士衡という官僚が入手したもので、豊臣秀吉が文禄・慶長の役(1592~98年)の時に日本に持ち帰り、その後、西本願寺歴代宗主の蔵書として保存され、現在は、龍谷大学に保管されている。西に小さく北から南に突起したアフリカ大陸には、巨大な湖水が描かれているが、これは雨期に氾濫し、あたかも内陸の海のようにサハラの南方地域を冠水させるニジェール川の伝聞が反映されたのではないかとの解釈がある。
2001年12月、アフリカ開発会議(TICAD)閣僚レベル会合の際に訪日した南アのジンワラ国民会議議長(当時)は、訪日前に学術論文の小さな記事で地図の存在を知り、「日本とアフリカの絆を証明する貴重な資料」として、日本外務省に会議場での展示を提案。これが実現し、ジンワラ議長は会議の挨拶で、「アフリカと日本は新しい友人ではない。我々は地図が示すように古い友人なのです。ただ、古い友人関係を新しいかたちで再構築しているだけ。」と語った。